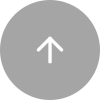「“やりたい”を起点にキャリアを築いてきた。」ゼロから文化をつくった社員第一号のリアルストーリー
2025.11.6 10:16
創業以来200%成長を続けるITコンサル企業、株式会社Grant。その立ち上げ期から事業と組織の両輪を支え続けてきたのが、社員第一号の山本幸(やまもと みゆき)だ。マスコミ業界からIT業界に飛び込み、ITコンサル→採用→広報と、自らの興味を起点にキャリアを切り拓いてきた。経営と現場をつなぐリーダーとしても奮闘するリアルストーリー。
■ 意欲と情熱がキャリアを動かし、組織を変えた
「採用も広報も、“誰もやっていないからやる”ではなく、純粋に“私がやりたい”と思って始めました。」
創業2期目の入社当時、Grantには採用も広報も存在していなかった。
それでも山本は自然とその領域に惹かれていった。
マスコミ出身ということもあり、「伝えること」への興味と感度が、人一倍強かったからだ。
「人の想いを言語化したり、見えない価値を形にするのがすごく好きなんです。
それがたまたま“採用”や“広報”という仕事だった、という感覚に近いですね。」

当時はまだITコンサル業務が主軸。
日中はクライアント案件を担当し、業務の合間や終業後に採用・広報の企画を進める日々だった。
勤務時間は長くなったが、不思議と疲れるという感覚はなかったという。
「楽しかったんです。誰に頼まれたわけでもなく、自分が“やりたい”と思って動いていたから。」
その熱量は社内外にも波及。
試行錯誤しながら運用を始めた公式X(旧Twitter)は、半年でフォロワー6,000人を突破。
「自分の言葉で伝える力」が、会社の認知を押し広げる原動力になった。

数字という明確な成果を出したことで、
社内からも「継続力」「発信力」「推進力」を認められるようになった。
当時は創業初期で、仕組みもルールもない中
ひとりで走り続けた経験が、いまの広報活動の礎になっている。
また、Grantはチャット中心のコミュニケーション文化。
発信に慣れていない社員も多い中で、
山本の挑戦は「想いを言葉にして届ける」文化を根づかせるきっかけにもなった。
SNSを通じて社内の価値観が可視化され、“発信すること=会社を育てること”という意識が少しずつ広がっていったのだ。
“やりたい”から始まった行動が、結果的に会社の文化をつくり、
いまのGrantの発信スタイルへとつながっている。
■ 採用も広報も”共感”という点でつながっている
それから徐々に採用業務の割合を増やしていった。
採用担当としてキャリアを歩みはじめた山本が気づいたのは、
「採用と広報は同じゴールを見ている」ということだった。
「採用も広報も、“伝える”仕事ではなく“惹きつける”仕事。
違うのは対象だけで、根っこにあるのは“共感をつくる力”なんです。」
求人広告を出しても響かない時代。
条件ではなく、共感できるストーリーが人を動かす。
山本はその構造に早くから気づき、採用の現場に「共感設計」という考えを持ち込んだ。
説明会は“プレゼン”ではなく“物語の場”、面接は“評価”ではなく“対話”。
その発想が、採用活動の質を変えた。

■ 広報責任者としての新たな挑戦
2025年10月、山本は正式に広報責任者に就任。
自分の“やりたい”を突き詰めてきた彼女が、いま組織の顔として再スタートを切った。
「これまで感覚でやってきた部分を、どう仕組みに変えるか。
いままさに壁にぶつかっている最中です(笑)。」
SNS発信やYouTubeなど、Grantが積み重ねてきた広報活動を、より戦略的に整備するフェーズ。
数値化しづらい“共感”をどう可視化し、再現性ある仕組みにしていくか——挑戦は続いている。

■ “共感資産”をつくるという発想
山本が新たに掲げたテーマが、「共感KPI」。
SNSやYouTubeでの反応を単なる数字ではなく、“どれだけ心に残ったか”を測る指標として再設計。
そこから採用・ブランディング・事業発信までを横断的につなげていく。
「発信って“伝える”ではなく、“残す”ことだと思っていて。
共感が残れば、行動が生まれる。行動が生まれれば、関係が続く。
その循環を仕組みにできたら、広報はもっと面白くなるはずです。」

■ 組織のロールモデルとして
マスコミ→ITコンサル→採用→広報。
ひとつの専門にとらわれず、自分の好奇心を道しるべにしてきた山本。
「やりたい」を起点に行動し続ける姿は、若手メンバーのロールモデルになっている。
また広報責任者でありながら、経営層とメンバーの間に立ち、組織の想いを言語化し、伝え、育てる役割も担う。
ときに橋渡し役として、ときに伴走者として——
企業文化の醸成とメンバーの成長を支える存在でもある。
「キャリアって、何をやるかより自分がどう在るかだと思うんです。
誰かの期待に応えるより、自分がワクワクする方へ動くと結果的に貢献につながる。
私の人生の意思決定における指標の一つでもあります。
今後も社会や組織の変化をポジティブに捉えて、自分自身も迅速にアップデートしてGrantのさらなる成長に貢献していきたいです。」